皆さん、こんにちは!サグラダファミリアやフラメンコで有名なスペイン!
そんな観光立国であるスペインが、ほんの数十年前まで独裁体制が続いていたことを御存じですか?
スペインが民主化したのは1975年。今からほんの40年余り前のことなんです。
長期にわたり独裁を敷いていた人物、その名もフランシスコ・フランコ。
日本ではあまり知られていない20世紀スペインと独裁者フランコについて、徹底解説いたします!
スペインの独裁者フランシスコ・フランコ
フランコが歴史に登場するのは1930年代のスペイン。
1930年代のスペインといえば、共和政の下で右派と左派が激しく対立し、暗殺や犯罪が横行する暗い時代だったのです。
そして1936年7月、膨張し続けた政治的な左右対立は左派軍人たちによる大規模な反乱にまで発展します。
反乱はすぐには収束せず、右派である軍部や労働者を中心とするナショナリストと、左派である共和政支持者との間での内戦となります。
これはまさに、スペインの危機的状況と言えますね!
そんな危機的状況である内戦下で頭角を現したのが右派であるナショナリスト陣営のフランコ将軍だったのです。
スペインの危機に現れた若き将軍
内戦が始まった頃、フランコはナショナリスト陣営の指揮官の1人に過ぎませんでした。
しかし、軍人としての実績があったために人気を集め、瞬く間に総司令官、そして国家元首となったのです。
1938年、内戦がナショナリスト陣営の勝利に終わると、フランコをトップとした体制が確立しました。
これが長く続く独裁体制のスタートとなります。
37年に及ぶ独裁体制
この独裁体制は驚くべきことに37年間も維持されたのです。
当時ファシスト政権が成立していたイタリアやドイツから、フランコは多くの支援を受けていました。
ピカソの代表作「ゲルニカ」でも知られている、ヒトラーが行ったスペインの都市のひとつであるゲルニカへの空爆は、この内戦中の出来事なのです。
第二次世界大戦が終結すると、国際社会では冷戦の幕が開けます。
この際にフランコは、スペインが反社会主義の立場であることを強く表明し、西側諸国に歩み寄ろうとします。
ファシズムという共通点のもと強く結びついていたドイツとイタリアが敗戦すると、今度は共産主義を嫌っているという共通点を前面に打ち出し、アメリカに歩み寄ろうとしたのです!
こうコロコロと立場を変えて、国際社会で上手くやっていけるものなのかと不思議に思いますよね。
筆者は国際情勢を上手く先読みすることがフランコの才能だったようにも感じます。
つまりフランコ体制は、社会情勢を巧みに利用し政治的立場を変化させることで長期間存続できたということができます。
そして1975年に彼が死去するまで、体制が揺らぐことはありませんでした。
フランコはいったいどのように、独裁体制を数十年にわたり維持したのでしょうか?
スペイン情勢を詳しく説明しながら、フランコの生涯と彼の独裁について徹底解説していきたいと思います!
フランコの生涯とスペイン

引用元:https://commons.wikimedia.org/wiki
フランコこと、フランシスコ・フランコ・バアモンデは、1982年にスペイン北部のガリシア地方で生まれました。
フランコの家系は、海軍と関わりの深いブルジョワ階級でした。
当然フランコも、将来は軍人になると期待されていたのでしょう!
陸軍兵として18歳から戦いに参加し、33歳という若さでスペイン史上最年少の将官となったのです。
しかしいくつかの記録では、フランコは若いころから成績や軍人としての素質が突出ていたわけではないと記されています。
様々な経験や努力が実った昇進だったのかもしれません。
そしてスペインの若き軍人フランコはどのように独裁者となっていくのか気になりますね!
混乱のスペイン
1930年代のスペインは共和国政府の下で、左派と右派が激しく対立していました。
また、様々な思想を持つ人々が対立し行動を起こしていたため、治安も悪化しており国内政治はとても不安定な状態でした。
当時のスペインでは無政府主義者、アナーキストと呼ばれる思想の人々が多く存在し、政治家や著名人が暗殺されることが頻繁に起きていたのです。
きっと人々の生活に漂う空気も、重く暗いものだったのではないでしょうか。
そして、国内政治を揺るがすような出来事が度重なったのです。
例えば、スペイン領モロッコではスペインの抑圧に耐えかねた原住民による反乱が頻発します。
そして当時モロッコに駐屯していたフランコは、この反乱を鎮圧することで順調にキャリアを積みました。
また、スペイン国内ではバスク地方やカタルーニャ地方に代表される地域ナショナリズムが活発化します。
地域ナショナリスト達は地域の自治拡大を求めて様々な運動を展開し、国内政治をますます不安定にさせました。
その他にも、社会主義者の主導により賃上げや労働環境改善のために労働運動が活発化します。
1934年には政府に対して各地で大規模な労働者による蜂起がおきます。
特にアストゥリアス地方での蜂起は、他と比べて長期的でより悲惨なものとなりました。
これを徹底的に弾圧したのも、フランコだったのです。
蜂起側の死者は1300人以上に上りました。
このように様々な危機に直面したスペイン!
共和政のもとで政府は十分に機能せず社会はとても不安定であり暴力的な雰囲気に包まれてしまいます。
社会不安が大きくなる中スペインの軍部は、左派勢力によって形成されていた政府の政治能力の低さを強く批判します。
そして軍部は主に共和政に不満を持っていた右派勢力と、結びつきを強めていきます。
こうして、軍部と政府の対立は増していくのでした。
スペイン内戦ぼっ発!
1936年7月、軍部は共和国政府に対して実権を掌握すべく、クーデターを宣言します。
スペインでは、クーデター宣言(プロヌンシアミエント)というものが存在し、武力的な行動に出る前に、クーデターの意思を表明するための宣言を行うのが一般的でした。
今回のクーデター宣言にも、武力行為を行わずに権力を掌握する狙いがありましたが、その目論見は外れてしまうのです。
スペイン各地で、労働者や共和政支持者たちが軍の蜂起を食い止めようと行動に出ます。
また、軍部のなかにも反乱に賛同せず共和国政府を支援する者もいました。
これによりスペインは、反乱軍側(左派)と共和国側(右派)が対立する内戦状態が生まれてしまいます。
まさに、状態が泥沼化してしまったということですね
フランコの台頭と内戦終結
反乱軍は、各地で軍人が蜂起を起こすことでスペイン全土を掌握しようと目論んでいました。
内戦当初、フランコもそれらの軍人のひとりに過ぎませんでした。
しかしフランコは、経験豊富な部隊を率いていたことや強い人脈を持っていたことなどから徐々に影響力を強めていきます。
そして、1936年9月には、フランコは最高司令官となるのです。
また、フランコは自身をトップとした単一政党を組織することで、思想の異なる様々な右派勢力を、内戦勝利のためにひとつにまとめ上げたのです。
そして、反乱軍にとって大きな追い風となったのが、ドイツ、イタリアというファシズム国家からの支援と、カトリック教会からのフランコ政権承認でした。
ピカソで有名なゲルニカへの空爆も、ヒトラーによる反乱軍支援の一環だったのです。
独裁政権だったドイツやイタリアがフランコを支援するのは当然のようなことだと思えますね。
しかしカトリック教会はなぜ、フランコを支援したのでしょうか?
その理由は、カトリック教会と共和国政府が対立していたからなのです。
カトリック教会は、教会に対して厳しい政策を行っていた共和国政府を良く思っていなかったため、右派勢力が集結していた反乱軍を支援したのです。
国外からも多く支援を受けていたナショナリスト陣営ですが、対照的に共和国陣営は常に支援物資が乏しい状態でした。
その理由は、イギリスやフランスなどの大国が国際紛争になることを恐れて不干渉を貫いたからです。
ヘミングウェイなどが参加したことで知られる義勇兵や唯一だったロシアからの支援も受けましたが、次第に共和国側は追い込まれていきます。
そして共和国側は善戦するも1938年の半ばには反乱軍側の勝利がほぼ確実となります。
1939年には、イギリスやフランスなどもフランコ政権を承認し、すでにフランスに亡命していた共和国側のトップも辞任してしまいます。
そして同年4月1日、フランコは首都であるマドリードにて内戦の終結を宣言したのでした。
フランコの独裁体制の始まりです。
世界大戦を上手くかわした
フランコ政権は成立当初から様々な困難に直面していました。
内戦に勝利したとはいえ、国内にはまだたくさん政権に反発する勢力がいました。
戦時中と変わらず社会を敵と味方とで区別し、反対勢力を武力で弾圧したのです。
3年にも及んだ内戦でスペイン国内は荒れ果て、インフラ整備や食糧不足などの課題もありました。
しかし、それだけではありません!
内戦終結から半年ほどで勃発したのが第二次世界大戦でした。
中軸国側であるドイツのヒトラー政権やイタリアのムッソリーニ政権からの支援を受けていたフランコ。
当然、中軸国側としての参戦を要請されますが、内戦の影響で国内が荒廃しきっていたことを理由に、その要請を断るのでした。
中立国という立場をとったスペイン。それでもなお、ヒトラーはフランコに参戦を要求しました。
そこで、最終的にスペインは「非交戦参戦」という中軸国寄りの立場を示しながら、実質的には中立を貫いたのです。
1942年頃には、中軸国側の戦況に陰りが見え始めます。
この状況に素早く反応したフランコは中軸国側と距離を置き始め、連合国側と融和的な関係を築こうとするのでした。
戦時中に国の立場を変えてしまうというのは、なかなか大胆な戦略のように思います!
このようにフランコは第二次世界大戦中、国際社会の動きを敏感に捉えながら、最後まで戦火交えることなく終戦を迎えたのです。
1945年6月、ドイツの降伏によりヨーロッパにおける第二次世界大戦は終わります。
国内政策に重きを置き、大戦に参加しなかったフランコ。
いったい国内でどのような政策を行っていたのでしょうか?
体制の国内政策
内戦が終結したからといって、フランコ政権は万全ではありませんでした。
経済は内戦によって大きなダメージを受けており、元共和国側の残党と戦闘になることもしばしばありました。
そんな落ち着かない状態の中、フランコ政権は支持基盤を固め、政治体制を確立する必要があったのです。
例えば、国家元首法というフランコが自由に法や政令を発布できるという法律が作られました。
フランコは軍事的だけではなく、行政的にも権力を独占したのです。
戦争の責任を追及する政治責任法やフリーメイソン弾圧法などの法律も制定します。
これらの法律は、反対勢力を抑圧するために作られました。
これは、内戦での勝者と敗者を戦後もしっかりと区別し、敗者が抑圧される社会が続くことを意味していました。
また、経済的にも危機的状況にあったため、自給自足を行うための政策や国家の積極的な経済への介入が行われました。
これらの様々な政策でフランコ政策の支持基盤は徐々に安定していきました。
しかし、内戦に勝利したフランコ政権にとって最も必要だったことは政権の正統性の確立です。
その大きな助けとなったのが、カトリック教会の支持です。
フランコ政権は内戦中から変わらず、カトリック教会との結びつきを強めていきます。
そして、フランコをただの指導者というだけではなく、歴代の偉人たちのようなカリスマ的イメージを国民に植え付けようとしたのです。
例えば、学校の壁には聖母マリアやキリストの絵と共にフランコの写真も飾られていたそうです。
国内での政権安定を実現し、第二次世界大戦もうまく乗り越えたフランコ政権。
しかし、時代は冷戦という新たな局面を迎え、フランコ政権にも次なる問題が浮上します。
国際的孤立
第二次世界大戦後、フランコ政権は連合国側に融和的な姿勢を取っていました。
しかし、民主主義国家ではなくファシズム政権というイメージがあったスペインに対する風当たりは強いものでした。
1945年7月には国民憲章が定められ、法の下での平等や一定の自由が保障されました。
この憲章は、スペインが民主主義を基本とする西側諸国に近づくために、スペインに対するファシズム的なイメージを弱める働きも担っていました。
しかし、国際社会からの態度は厳しく、1946年12月にはスペインが国連機関から排斥されてしまうのです。
フランコ政権にとって危機的状況のような気がしますが、フランコはこの国際的孤立を利用し、国民の愛国心や国内の統一感を向上させようとします。
ここでもフランコはピンチをチャンスと捉え、奮闘したのです!
そして、東西対立が激化する中でスペインに対する国際社会の認識は少しずつ変わっていくのでした。
西側諸国の一員へ!
1950年代には、ソ連による原爆実験の成功やベルリン封鎖などの出来事が相次ぎ、ソ連の影響力が拡大していた時期でした。
西側諸国は共産主義の脅威を目の前にして、地理的にも重要であったスペインを国際社会に受け入れざるを得なくなったのです。
1950年にはスペインが国連に復帰、1953年にはアメリカとの軍事協定の締結など、徐々に国際社会へ参加することに成功したのです。
国内でも戦後から徐々に経済が復興し、遅れていた工業化も進みました。
特に60年代には、ヨーロッパ経済と結びつきを強めたことで、奇跡の経済成長と呼ばれる急成長を遂げました。
当時のスペインの経済成長率は日本に次ぐ世界第二位だったのです!
国際社会への復帰に成功し、経済も成長したスペインでしたが、民主主義国家ではないという理由でEC(EUの前身であるヨーロッパ共同体)には参加できませんでした。
フランコ体制の中で成長したスペインでしたが、独裁体制下では同時にたくさんの課題が残されたままでした。
そしてついにフランコ体制も終盤に差し掛かります。
それでは、どのような課題があったのかについてご紹介いたします!
フランコ死後の体制存続を目指して
フランコ体制末期は、経済成長と共に形成された中間層による反体制運動や労働運動が激化した時期でもありました。
以前のように、武力だけで反対勢力を押さえつけることが難しくなっていたことに加え、フランコ体制の正統性を保つことも難しくなっていました。
内戦を知らない世代にとって、内戦の勝利者ということはあまり意味を持たなくなっていたのだと筆者は考えます!
ここで一番大きな問題だったのがフランコの死後、どのように体制を維持していくかということです。
フランコは自分の後継者にはスペイン前国王の孫である不安・カルロスを指名します。
なぜ、急に国王の孫が後継者に指名されたのでしょうか!
もちろん、国王の他にもフランコの右腕だったカレーロ・ブランコという人物などがいました。
首相などの政府の役職はフランコ体制に長年尽力した人々に引き継がれることをフランコも想定しての決断だったのです。
しかし一番大きな理由はほかにありました。
フアン・カルロスは幼いころからフランコと交流を持っていました。
そのためフランコは、自身の政治理念をしっかりとフアン・カルロスに教育することに成功したと考えていたのです。
フランコは自身の作り上げた体制を、国王という十分な正当性があり、なおかつ自分の理念を受け継ぐものに託そうとしたのでした。
そしてついに、1975年11月フランコは82歳を目前に死去したのでした。
フランコ体制の終焉と民主化
フランコの死後、フランコ体制の存続はほぼ不可能になっていました。
フランコ体制継続に尽力していたカレーロ・ブランコが暗殺されるテロ事件が起きたことや、フランコの死後に反体制運動が過激化したことなど様々な要因がありました。
しかし、一番大きいのは国王自身が民主化を望んだということです。
つまり、フランコのフアン・カルロスに対する期待はある意味裏切られてしまったということですね。
1976年、反体制運動が高まる中で国王はアドルフォ・スアレスを首相に抜擢します。
彼は民主化の立役者とも言われている人物で、スアレスの下でスペインは民主化に成功するのでした。
余談ですが、現在のマドリードの国際空港の名前も彼にちなんでアドルフォ・スアレス空港と命名されています!
こうしてスアレスの数々の改革でフランコ体制は完全に終焉を迎えました。
そんな彼の生涯とフランコの生きたスペインを皆さんはどのように感じましたか?
フランコ体制には、評価されるべき側面と不平等で非人道的な側面などの様々な要素を合わせ持っています。
私が特に興味深いと感じる、フランコ体制や近代スペイン史に関することを、最後に少し紹介したいと思います!
ここが面白い!近代スペイン史
ここまで、フランコ体制についてご紹介しましたが、皆さんはどのような感想をお持ちですか?
ほんの数十年前に社会体制が激変したスペイン。
現在、フランコ体制はどのような体制だったと考えられているのでしょうか?
フランコ体制の本質って?
フランコ体制はフランコを中心とした独裁体制でした。
しかし、一言でファシズム体制だと言い切ることは出来ません。
フランコを党首とした政党は、元々内戦の勝利という共通の目的を持つ人々の集まりに過ぎませんでした。
ファシストもいればカトリック勢力もいる、様々な考え方の人々が集まった政党なのです。
単一のイデオロギー、つまりひとつの考え方を共有するファシズム政党とは少し異なっていると思います。
そして、第二次世界大戦後には、フランコはスペインが民主主義国家であると主張します。
実際に、国民憲章などが制定されフランコ基本法という憲法も制定されました。
見せかけではあったといえ、フランコ体制は民主主義的な要素を少し含んでいました。
一言で彼の政治がどんなものか表すことができないフランコ体制。
しかし立場やイデオロギーを変化させながら、数十年にわたり体制を維持したことが驚きですね!
フランコとスペイン王家の関係
フランコ体制の後継者として指名されたフアン・カルロス。
独裁者の後継者が王家の人間というのは、珍しいことではないでしょうか?
フランコはなぜフアン・カルロスに自分の体制を任せようとしたのでしょう。
先ほども少し言及しましたが、フアン・カルロスは幼い頃よりフランコと交流を持っていました。
それだけではなく、長い間フランコの影響力が及ぶところで生活していました。
そして帝王学をしっかりと教えられていたため、フランコは彼が自分の意思を引き継ぎしっかりと国を治めると考えました。
この場合の帝王学とは、王家の人が教わる国を継ぐための教育のことです。
このような理由により、独裁者の跡継ぎが王家の人間となったのです。
筆者は、王家と独裁者と聞くと、敵と味方なのかと勝手に想像してしまっていたので、かなり驚きました。
しかしフアン・カルロスの即位後、スペインはすぐに民主化してしまったのです!
最後に簡潔にこの民主化についてご紹介して今回の記事を終わりたいと思います。
民主化は異例の体制移行
フアン・カルロスは即位に際して、フランコの作った法令を守るという誓いを立てました。
しかし、民主化を望む国民の声や、自身に強力な後ろ盾がいなかったことなどから、フアン・カルロスは民主化を行おうとしました。
しかし、フランコによって国王の地位を得た彼にとって、民主化というのは自身の地位も脅かされてしまいます。
また誓いを立てていたことも大きな障壁となります。
八方塞がりなのか!?と思いますが、ここで登場したのがアドルフォ・スアレス首相なのです。
先ほど少し述べた、民主化の立役者です!
彼はなんと、フランコ時代から続く議会で次々と改革を行い、最終的には民主化を実現したのです。
つまり、体制を独裁から民主主義に移行したということになります!大きな騒ぎなく、独裁から民主化が成功した事例はそう多くはありません。
そして、フランコは完全に過去の独裁者となったのです。
【フランコ政権】フランシスコ・フランコをわかりやすく解説!スペインの長期政権!まとめ
皆さんはこの、フランコという人物についてどのように感じましたか?
筆者は、一言では表せない評価すべき点と追及すべき点とが混在するとても複雑な人物だと考えています。
彼の人生と近代スペイン史を通してさらにスペインに興味を持っていただけると幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
【参考文献】
スペインの歴史を知るための50章 立石博高 明石書店 2016
スペイン史10講立石博高 岩波書店 2021
- スキピオ・アフリカヌス・偉大な将軍の栄光と悲哀を解説!
- 【この陣形驚愕】ハンニバル・バルカの栄光と悲劇!
- 皇帝ネロの人生とは?わかりやすく解説!母までも殺し最後は悲しく散ったネロ
- ミケランジェロの彫刻作品と生涯をわかりやすく解説します!
- 黒死病(こくしびょう)とは?簡単にわかりやすくペストを解説。発見者は日本人だった!
- フリーメイソンの起源とは!世界を操る悪魔か?救世主なのか?謎多きグループの起源を解説!









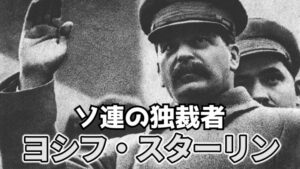



コメント